始めに
子供の頃に、いわゆる文学と呼ばれるものに触れた初めての作品は夏目漱石の「吾輩は猫である」でした。その次が、芥川龍之介の「蜘蛛の糸・トロッコ」で、芥川龍之介の児童向け文学作品が収録されている本でした。
芥川龍之介のこの短編集は好きで、何度か繰り返し読んだ記憶があります。ただ、子供向けの装丁の大きめのハードカバーの本で、大人になった後、どのように処分されたのかは覚えていません。捨ててしまったか、売られたか、あるいはどこかに寄付がされたかもしれません。
この時の読書体験がきっかけで、芥川龍之介の有名どころは、だいたい学生時代に読んだのではないかと思います。文学というと、少しとっつきにくいイメージもありましたが、芥川龍之介の小説は(後期のようなものを除いて)プロットのしっかりしたストーリーが多くて読みやすいんですよね。子供の頃に読んだ作者という記憶もあって、比較的入りやすさはあったかなと思います。
先日、ふと芥川龍之介の本を読み直したくなって、文庫本はいくつか持ってるんですが、児童向け文学の本は先述の通り、どこかに行ってしまったので、改めて買い直しました。
この記事ではその中で杜子春にフォーカスをあてて、内容を考察したいと思います。※なお、有名作品ですし短編ですので、ネタバレなどの考慮はしておりません。
概要
芥川龍之介の杜子春は1920年に、雑誌「赤い鳥」に掲載された児童向け短編小説です。「赤い鳥」は童話と童謡の掲載されていた雑誌で、芥川龍之介の他にも、有島武郎や菊池寛といった有名作家も寄稿していました。
芥川龍之介はこの雑誌に杜子春をはじめ、蜘蛛の糸や魔術などの児童向け文学を発表しています。
少し長いですが、Wikipediaよりあらすじを引用します。
唐王朝の洛陽の都。ある春の日の日暮れ、西門の下に杜子春という若者が一人佇んでいた。彼は金持ちの息子だったが、親の遺産で遊び暮らして散財し、今は乞食同然になっていた。
そんな彼を哀れんだ片眼眇(すがめ、斜視)の不思議な老人が、「この場所を掘る様に」と杜子春に言い含める。その場所からは荷車一輌分の黄金が掘り出され、たちまち杜子春は大富豪になる。しかし財産を浪費するうちに、3年後には一文無しになってしまうが、杜子春はまた西門の下で老人に出会っては黄金を掘り出し、再び大金持ちになっても遊び暮らして蕩尽する。
3度目、西門の下に来た杜子春の心境には変化があった。金持ちの自分は周囲からちやほやされるが、一文無しになれば手を返したように冷たくあしらわれる。人間というものに愛想を尽かした杜子春は老人が仙人であることを見破り、仙術を教えてほしいと懇願する。そこで老人は自分が鉄冠子という仙人であることを明かし、自分の住むという峨眉山へ連れて行く。
峨眉山の頂上に一人残された杜子春は試練を受ける。鉄冠子が帰ってくるまで、何があっても口をきいてはならないというのだ。虎や大蛇に襲われても、彼の姿を怪しんだ神に突き殺されても、地獄に落ちて責め苦を加えられても、杜子春は一言も発しなかった。怒った閻魔大王は、畜生道に落ちた杜子春の両親を連れて来させると、彼の前で鬼たちにめった打ちにさせる。無言を貫いていた杜子春だったが、苦しみながらも杜子春を思う母親の心を知り、耐え切れずに「お母さん」と一声叫んでしまった。
叫ぶと同時に杜子春は現実に戻される。洛陽の門の下、春の日暮れ、すべては仙人が見せていた幻だった。これからは人間らしい暮らしをすると言う杜子春に、仙人は泰山の麓にある一軒の家と畑を与えて去っていった。
Wikipediaより
ストーリーとしてはほぼこれで全部ですね。児童向けで短い作品ではありますが、改めて読み直して、簡潔だけれども、明瞭な文章で仙人や地獄などの芥川の想像世界の描写が行われていて面白いです。
ストーリーから見られるメッセージは非常に単純で、分かりやすいと思います。素直に話を受け取れば、お金で贅沢をして作った人間関係は、そうやってできた人間関係はお金がなくなってしまえば、見向きもしてくれなくなる。地獄で責め苦を受けても、相手を思いやる母親のように無償の愛こそが尊いもので、それはお金では手に入らない。そのような「何よりも人間らしく」暮らすことが大切だ、というメッセージが見られます。
このなかで鉄冠子は、主人公の杜子春に試練を与え、気づきを促すきっかけを与える師匠のような役割を持っています。しかし、行動要因の分かりやすい杜子春とその母親に比べて、鉄冠子の行動要因はぱっと見よく分かりません。鉄冠子は、なぜ、杜子春に対して、声をかけたのでしょうか?杜子春に何度も黄金を与える一方で、試練について、「もしお前が黙っていたなら、おれは即座にお前の命を絶ってしまおうと思っていた」という厳しい一面も覗かせます。この記事では鉄冠子に関する、二つのイメージについて、見てみたいと思います。
鉄冠子のイメージ
筆者は、鉄冠子には以下の二つのイメージがあるのではないかと考えています。
- 父性
- 死のイメージ
それぞれ見ていきます。
父性としての鉄冠子
まず、鉄冠子の行動を洗い出してみます。
- 財産を使い果たした杜子春の前に現れて、黄金を与える
- 弟子になりたいという杜子春の願いを聞き入れて、決して声を出してはいけないという修行を与える、実際には人間的成長を与えるような体験を(幻覚で)見せる
- 泰山の南のふもとの一軒の家を杜子春に送る
これらの行動は、非常に父性を強く感じるものになっています。
何も条件なく黄金を与えることは、父から息子に小遣いを与えるイメージに近く、何度も財産を使い果たした杜子春を修行にやる様子は、子供を叱責して厳しくあたる父親の様子にも思えます。また、最後に家を譲って去る様子は、父から子への遺産の相続との類似性が感じられます。
杜子春の論文などを読んでいると、父親の不在を指摘されているものがあります。実際には全く出てこないわけではなく、母親と一緒に畜生道に落ちており、動物の姿として杜子春の前に現れます。しかし、杜子春に声をかけるのは母親であり、その時の描写は「母親はこんな苦しみの中にも、息子の心を思いやって、鬼どもの鞭に打たれたことを、怨む気色さえも見せないのです。大金持ちになれば御世辞を言い、貧乏人になれば口も利かない世間の人たちに比べると、何という有難い志でしょう。何という健気な決心でしょう。」と母親にフォーカスを当てられており、父親の存在感は全くありません。
芥川は複雑な家庭に育ったので(詳しくは省略)、作家論的に読めば、家庭の事情を作品世界に反映させたという読み方もできるかもしれませんが、ここでは、テキスト論的に見てみます。
これには物語上の役割として鉄冠子とイメージが重複することを避けるため、との指摘もありました。父性的な役割を鉄冠子が担っている以上、似たような役割のキャラクターを増やすのは、混乱をきたすからではないかということです。
その考え方はなるほどなと思いつつ、さらに、そうなると鉄冠子の行動に一貫した理由もつきます。先述した通り、鉄冠子の行動は父親的です。逆に言うと、そうでもなければ、黄金を与えるなど、なぜ何の利もないそのような行動をとろうとしているのか疑問がつくような箇所もあります。一応、本人の口からは、「どこか物わかりが好さそうだったから、二度まで大金持ちにしてやった」という言葉がありますが、それにしては、ずいぶんな大盤振る舞いのように思えます。
しかし、父親として鉄冠子を捉えれば疑問は解消します。黄金を与えるのは息子を甘やかしているからであり、結果として、人間的成長がなく、人間不信にまで陥ってしまった息子に試練を与えることで、人間的成長を促す。息子の成長を確認した後は、安心して家を与えて去っていく。物語を通して、鉄冠子というキャラクターの行動に筋が通ることになります。
もっとも、鉄冠子は仙人であるので、人間の価値観で測ろうとすることが間違っているのかもしれませんし、鉄冠子が父性的な役割を持つなら、なぜ、わざわざ地獄で転生した父親も登場させたのかという疑問は残りますが、少なくとも物語的に父性的な役割を鉄冠子が担っていることは間違いないとわれます。
死のイメージとしての鉄冠子
もう一つ、鉄冠子には死のイメージがまとわりついています。この作品の死に関する描写部分を抜き出してみます。
- 杜子春は冒頭で「一そ川へでも身を投げて、死んでしまった方がましかも知れない」と悩んでいた(ところに鉄冠子が現れた)。
- 人間界に嫌気がさして、仙人界に行こうとする(≒この世の未練が喪失している)。
- 杜子春は(幻想の中で)殺され、地獄に連れていかれる。
- 死んでしまい、動物に転生した両親が登場する。
- 「もしお前が黙っていたら、おれは即座にお前の命を絶ってしまおうと思っていた」という鉄冠子の言葉。
上に書いた通り冒頭から、杜子春は死んでしまおうかと悩んでおり、読者には生きるか死ぬかという状況に主人公があることを突き付けられます。さらに、二度、金持ちになり贅沢を尽くしても、その後、没落したら、自分に見向きもしない人間界に嫌気がさし、修行(幻覚)の中で殺され地獄に行く体験が描かれます。
杜子春のこれらの体験は、最初の状況以外、鉄冠子がきっかけになっていますね。黄金を与えられたことで、贅沢を極めたが、人間界に嫌気をさしてしまうことも、地獄に連れていかれたのも、意図はともかく、鉄冠子がきっかけになっています。どことなく、人間界ではない死の世界に杜子春を誘っているようにも見えます。
また、物語の最後に「泰山の南の麓にある一軒の家」を鉄冠子は杜子春にプレゼントします。この家については、なぜ泰山だったのかという議論があります。その理由を見ると、不吉なイメージがさらに増幅されます。
鉄冠子いわく「桃の花が一面に咲いているだろう」、とさわやかなイメージで物語を締めくくるエピソードのようにも思えます。しかし、泰山という場所は古来中国では黄泉の国につながる山であるという言い伝えがあるようです。そのため、泰山という場所は人間界よりも死後の世界に近く、その場所に家を与えるという行為は、杜子春に対しての(人間界に戻れるかという)最後の試練を意図しているというような指摘があるのです。
泰山という山をわざわざ芥川が選んだとすれば、文章で描写されているさわやかさの裏に何かの意味を込めた可能性はあるのかもしれません。それは、果たして、書かれたようなさわやかな意味があったのでしょうか。
さらに、鉄冠子が黄金を与える箇所も、不穏な読み方が出来ます。どういうことかと言うと、鉄冠子は杜子春に黄金を与える時、頭、胸、腹、と身体の部位にあたるところの影を掘るように指定してきます。ここで指定しているところが身体の部位というところがポイントで、身体的な表現は鉄冠子の描写の中でも出てきますが、それは、鉄冠子は片目眇であるとされていることです。
片目眇とは、片目が斜視(見えない)であることで、鉄冠子は身体の一部である目を欠損しているという描写になります。ちなみに杜子春は中国の古伝である杜子春伝を元に作成されており、元の話と比較された研究も多数存在しますが、そこで、杜子春伝の鉄冠子が片目眇であるという描写はありません。芥川のオリジナルの設定です。
それを踏まえて改めて黄金を与えるシーンを見てみるとどうでしょうか。片目を欠損した老人が、指定した身体の部位にあたる影の場所を掘ってみると、黄金が現れる。これは、まるで、怪談話に出てきそうな展開ではないでしょうか?果たして、杜子春がそのまま黄金を受け取っていき、身体の全てが指定されつくしたとき、杜子春自身は無事に済んでいたのでしょうか。
まとめ
鉄冠子という人物にフォーカスして、そのイメージについて述べてきました。鉄冠子は超越的な存在として描かれ、鉄冠子に人の道を諭すような発言はありますが、内面描写はないため、多様な見方が出来るのではないかと思います。
ただ、いずれにしても、これらのイメージは物語のメインテーマである杜子春の成長、人間的に生きるとはどういうことかというテーマを印象的に浮かび上がらせる役割を持っているのではないかと考えられます。人間に失望して死の淵に立ち、人の道を捨て仙道に向かおうとしていた杜子春が親の愛を見て、踏みとどまることになる。死という人としては最大級の不幸を身近に感じる中で起こる体験だからこそ、この親の人間的愛情が鮮やかに浮かび上がるのではないかと思えました。
以上、芥川龍之介「杜子春」についての考察でした。児童文学と言われる内容ながら、深く考察する余地のある作品だと思います。読んだことある方も多いかもしれませんが、また読み直してみると違った見方もできるかもしれません。
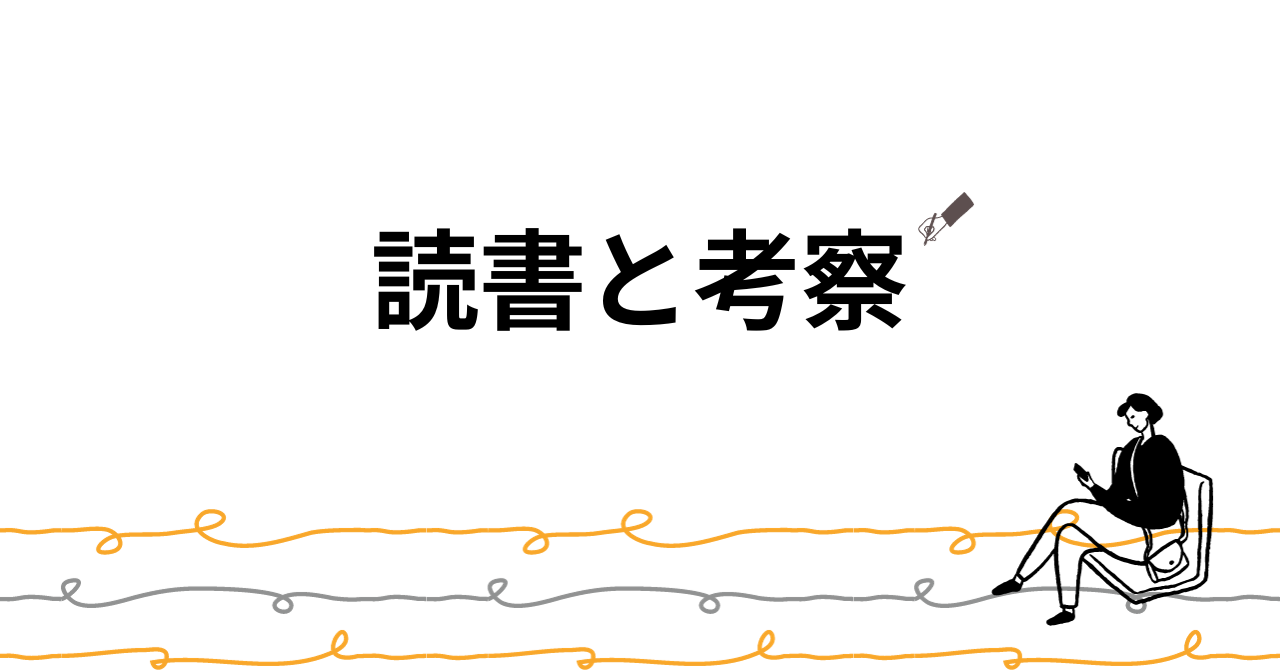

コメント