はじめに
ねじまき鳥クロニクルは1994年に第一部泥棒かささぎ編が出版された村上春樹の長編小説です。三部構成で新潮文庫の文庫本も一部ごとに出版されていて全三冊と一般的な小説と比べても長大な物語となっています。
村上春樹の代表作の一つと言ってもいい小説で、おそらく、村上春樹のファンに好きな小説を聞いてあげる人も多いでしょうし、論文などを検索してみると相当数の論文が出てきます。
その長さに見合うだけの重厚な物語になっていて、メインとなる主人公のオカダトオルの物語のほか、間宮中尉、ノモンハンの動物園の獣医(赤坂ナツメグの父親)など、ほかの登場人物を目線とした過去の物語のイメージが主人公の物語のイメージと繋がって、深い小説世界が描かれた物語です。
小説のストーリー
小説のメインとなるのは、現代、といっても1980年代の日本に住むオカダトオルという男の物語です。オカダトオルはそれまで働いていた法律事務所を辞めて、専業主夫として妻の稼ぎを頼りに生活をしています。働き先を探していますが、そこまで真剣に探していないために見つかっていません。
物語はオカダトオルに電話がかかってくるところから始まります。電話の主はオカダトオルのことを知っているようですが、オカダトオルは電話の主が誰なのかわかりません。いたずら電話とも思えるような卑猥な内容にオカダトオルはまともにとりあおうとはせず、電話を切ってしまいます。
また、電話がかかってきますが、今度は妻のクミコからのものでした。クミコは最近いなくなってしまった猫のことを気にかけており、主人公に猫を探すように話します。あまり乗り気ではない主人公でしたが、妻が真剣に猫を探すよう話をしてくるため、しぶしぶ、妻の意見に従って路地に猫を探しに行きます。
物語の始まりはこのように主人公オカダトオルの描写から始まります。第一部はオカダトオルと妻との関係描写や猫探しをする中でちょっと変わった人々との出会いが主軸になります。
話が大きく動き出すのは第二部の冒頭で、突然、何の前触れもなく妻のクミコが失踪することになります。といっても失踪の要因はわりとすぐに判明します。実はクミコは浮気をしていて、しかし、その浮気が終わるとともに、もう夫のもとにはいられない、として、オカダトオルの元を離れてしまいます。
クミコは手紙の中で、トオルと別れたいわけではないが、もう一緒にはいられないと思っていること、自分が自分とは異なる感覚があったことなどを語ります。しかし、トオルはそのことを認めず、妻を救い出すために動き出すことになります(こう簡単に書いてしまうとトオルが少し異常なストーカーっぽく聞こえるかもしれませんが、小説の中ではもう少し複雑な事情や心情が書かれています)。
妻のクミコを物理的に現実世界で連れ戻すことは難しいと考えたトオルは、己の精神世界にクミコを救い出すヒントを探しに行きます。具体的には井戸の底に(物理的に)降りて行って、自分とクミコの身にそれまで起こった様々な事件を思い出します。そして、過去を回顧する中で、トオルの中で精神世界に踏み込んでいく力が芽生え、壁を越えてその世界の中からクミコにアプローチする方法を取ります。その過程で、クミコを閉じ込めていた精神世界の中にある暴力的な存在に立ち向かっていくことにもなります。
物語の構造
村上春樹の小説は非常に文体が読みやすく、すらすらと読める一方で、物語は複雑で解釈が難しいものが多いと一般的には言われています。この小説についても、まさにその通りで、文体自体は簡易なものの、物語はオカダトオルの物語以外にも登場人物の語る様々なサブストーリーが織り重なっているため、細部まで読み込むのはなかなかに骨の折れる作業です。
しかし、メインとなるオカダトオルの物語の構造は概観だけで見ると、かなり容易にとらえることができます。とうのも、これはオカダトオル(主人公)が悪の力を行使する綿谷昇(敵対者)から妻であるクミコ(王女)を取り戻そうとする物語と要約はできてしまうからです。括弧の中に書いたのは、ウラジーミル・プロップの物語論の7つの行動領域に当てはめた役割ですが、その外観は非常に童話的とも言える分かりやすい物語です。主人公を助ける加納マルタ・クレタ、赤坂ナツメグ・シナモン、また、助けるという言い方が正しいかは微妙ですが、間宮中尉や笠原メイなどは贈与者や助力者ともいえるでしょう。
このように、ある意味では分かりやすいはずの物語が、なぜ、複雑になってしまうかと言うと、論理的な連続性がなされていないからですね。この物語では、なぜそうなるのか、その後どうなったのか、という説明が驚くほどなされません。ほとんどの場合で、作中の人物が言うように、そうなるからそうなのだというような、物語としては少々強引とも思える程、論理的な説明が省略されています。
例えば、主人公はなぜ井戸の底に降りるのか、井戸の底で考え事をすることがなぜ妻を取り戻すことになるのか、壁を抜けるとはどういうことなのか。小説の中でその説明はなされず、それがそういうものであるという前提で物語は進んでいきます。この小説を解説した記事や論文などを読んでいくと、無意識の暗示だとか集合的無意識の表現だとか書かれていて、小説の表現として、それはそうなんだろうなと思いますが、ストーリーの納得感という意味では読者への説明を放棄しているようなところが多いです。
まとめると、その道中の論理性や説明性は極端に低い(なぜ、妻を取り戻すために井戸に潜るのか?など)のですが、しかし、小説の大枠の構成は主人公が妻を取り戻すために奮闘するという目的の分かりやすさと、村上春樹の文体をはじめとした優れた小説の技法により、なぜ?という疑問は大量に生まれつつも、なぜか最後まで読み切ってしまうという不思議な読書体験が経験できます。
主人公の属する世界
この論理の断絶について、当然、村上春樹も意図して書いているものと思われます。その意図のヒントとなりそうな点として、作中で予知能力のような超常能力を持つ本田さんが主人公について、次のように述べる場面があります。
「あんたはあるいは法律には向かんかもしれんな」
ねじまき鳥クロニクル 第1部泥棒かささぎ編 より
(中略)
「法律というのは、要するにだな、地上界の事象を司るもんだ。陰は陰であり、陽は陽であるという世界だ。我は我であり、彼は彼であるという世界だ。<我は我、彼は彼なり、秋の暮れ>。しかしあんたはそこには属しておらん。あんたが属しておるのは、その上かその下だ」
(中略)
「どちらがいいどちらが悪いという種類のものではない。流れに逆らうことなく、上に行くべきは上に行き、下に行くべきは下に行く。(中略)流れのないときには、じっとしておればよろしい。流れにさからえばすべては涸れる。すべてが涸れればこの世は闇だ。<我は彼、彼は我なり、春の宵>。我を捨てるときに、我はある」
ここで、本田さんは主人公を地上界に属していないという指摘をしています。そして、主人公は法律事務所で働いていましたが、物語の開始直前に辞めて(働こうという意思はあるものの、何をしたいというものがなく成り行き的に)主夫になっています。
本田さんによると、地上界は我は我、彼は彼である、という論理的な私たちが生活する通常一般的な世界のことを指していると思われます。一方で、その上かその下というものははっきりとはわかりませんが、我は彼、彼は我、とあるように、一般的な論理の働かない異界のようなものをイメージさせています。
この二項対立のような世界観は、作中を通して、イメージが繰り返される世界観であり、もっとも分かりやすい対立(それは必ずしも対立する必要はないと思いますが、メインストーリーの中で描かれる対立)としては、地上界の上か下にいる主人公と地上界の代表のような存在の綿谷昇の対立です。
主人公オカダトオルと綿谷昇は、特別な理由はなくとも(おそらく本能的なレベルで)お互いを嫌いあっている仲ですが、普段は交流があるわけではなく、お互いに放っておける存在ではありました。ところが、クミコの失踪をきっかけに二人の対立は深まることになります。綿谷昇はクミコの失踪の理由(不倫をして、家をでていった)を主人公に語り、離婚の要求を突き付けます。それに対して、主人公は失踪に関する様々な疑問をクミコから直接語られていないことを理由に突っぱねます。
この時、綿谷昇は主人公のことを次のような言葉で攻撃します。
「最初に君に会ったときから、私は君という人間に対して何の希望も持ってはいなかった。君という人間の中には、何かをきちんとなし遂げたり、あるいは君自身をまともな人間に育てあげるような前向きな要素というものがまるで見当たらなかった。(中略)君たちが結婚してから六年経った。そのあいだに、君はいったい何をした?何もしてない――そうだろう。君がこの六年のあいだにやったことといえば、勤めていた会社を辞めたことと、クミコの人生を余計に面倒なものにしたことだけだ。(中略)はっきり言ってしまえば、君の頭の中にあるのは、ほとんどゴミや石ころみたいなものなんだよ。」
ねじまき鳥クロニクル 第2部予言する鳥編 より
なかなか苛烈な言葉で批判しています。
この綿谷昇の批判は、実はそこまで的を外していません。彼の言っていることは事実ではありますし、おそらく一般的に見たとき、主人公は仕事を辞めて妻の給料で生活をしているヒモのようにも見えます(主夫も立派な仕事だといった議論はここではいったん置いておきます)。妻を取り戻そうとする姿勢にしても、そういった経緯のある男が、妻に浮気をされて家を出ていかれる、というストーリーは「世間によくあること」です。下手をすれば、未練を断ち切れないストーカーまがいの男であるようにすら見える可能性もあります。小説のストーリー上でクミコが主人公を今でも愛していると手紙で伝えたり、浮気のことも、抗えない力が働いていた可能性が示唆されていたり、クミコの深層心理が電話の女として助けを求めていたりと、「そう簡単な話ではない」ことが読者には伝わってくるので、そのような印象は持たないですが、客観的に物語の事象を確認していくと、綿谷昇の言うことは一理ある指摘なのです。
地上界に属し、社会の論理で主人公を攻撃する綿谷昇に対して、主人公側の地上界の上か下に属している人間は、社会の論理とは別の世界で戦うことで、綿谷昇に対抗します。この小説では不思議な力や性質を持ったキャラクターが大勢登場します。井戸に入ることで無意識の領域に入り込める主人公はじめ、加納マルタ・クレタ姉妹、本田さん、間宮少尉、赤坂ナツメグ・シナモン親子。彼らは、社会の論理からはやや逸脱した感性や能力を持っており、その関わり方は様々ですが、主人公を助けて導く役割を持っています。
この小説に対して、時々面白くないという批判的な意見を見かけることがありますが、結構納得できる意見ではあります。おそらく、この超常的な世界のことに対して、ほとんど説明がないことが、その要因になっているのではないでしょうか?現実世界を描写されているところに説明なくファンタジーな要素が組み込まれていると、困惑してしまいますし、なぜ?という問いをあまりに無配慮に放置され続ける感覚がそうさせるのではないかと思います。
この対立が描く意味
さて、小説の中の地上界とその上か下という二項対立を見てきましたが、では、この対立の意味を考察していきたいと思います。
まず、一つ重要なポイントは、地上界代表の綿谷昇はこの小説において、何か大きな悪の塊の象徴としても描かれていることです。作中で綿谷昇自身が明確な悪を為すことは実は少ないのですが、作中で象徴的に描かれるのは過去の戦争の描写でしょう。作中で間宮中尉、本田さん、赤坂ナツメグと様々な人物の語りを通して戦時の描写が為されますが、そこには暴力的な悪の描写が多く描かれます。いくつかあげてみましょう。
- モンゴルの兵士によって皮膚を剥がされて殺される山本の物語(間宮中尉の長い話)
- 関東軍の指令によって、殺処分される新京の動物園の動物(動物園襲撃)
- 皮剥ぎボリスによるシベリア収容所の支配(ほかの人々に想像をさせる仕事、他)
これらの悪の描写は、社会システムの中で起きた戦争による悲劇です。皮剥ぎはロシアの将校に命令されて為されますし、動物は軍からの命令により殺され、ボリスの支配はシベリアの強制労働の中で行われることです。そして、作中、綿谷昇は選挙に立候補するという形で、社会システムに対しての力を強めようとする描写があります。そして、いくつかの描写は綿谷昇を通して、これらの悪による悲劇が繰り返される可能性が示唆されます。
これらのエピソードは綿谷昇と戦争時の悪のイメージを強く結びつけざるを得ません。主人公が感じていますが、政治を通じて綿谷昇が何を成し遂げたいのか、いまひとつ見えない、ということも不気味さを増長しているように思えます。また、作中で書かれてもいますが、この過去の戦争が今の主人公をはじめ登場人物たちを繋げているという描写も含まれます。綿谷昇の叔父は、陸軍参謀本部に勤務して、満州国やノモンハンの戦争に関係していた事実もあります。主人公らの時代と戦争の時代の話は独立しているわけではなく、円環のようにつながっているものなのです。
村上春樹は明らかに作中で悪のイメージを随所に描写し、その悪との対峙をする人物を何人も用意しています。主要な人物としては、間宮中尉と動物園の獣医、そして主人公のオカダトオルです。前述した地上界とその上か下の対立という観点は社会システムの中で為されてしまう巨大な悪に対しての対峙、という観点で見ることができるのです。
主人公の対抗
作中で悪の力は巨大です。皮剥ぎボリスの話の中であるように、その力は徐々に気づかぬうちに支配の中におかれて、人々から対抗する力を奪っていくように思えます。では、そのような巨大な力を持つ悪に対して、主人公のオカダトオルはどのような対応をとるのでしょうか?
これについては、一つ面白い論文があって、こちら(壁を抜ける「物語」――『ねじまき鳥クロニクル』論―― 北島咲江)で綿谷昇のやっていることを単純な物語として語ることという指摘があります。以下、論文から引用します。
この場面(引用者注:トオルにクミコとの離婚を迫るために会話をしている場面)でノボルが行っていることは二つある。一つはトオルが秩序づけられないクミコの失院という出来事を単純な「物語」にしてしまうことだ。ここでノボルは、クミコとの結婚がいかに簡単なことであるかを示すとともに、離婚までのお膳立てがすべて整っていることを伝えている。
壁を抜ける「物語」――『ねじまき鳥クロニクル』論―― 北島咲江
ノボルが望んでいるのは、トオルが離婚に承諾することであり、それはノボルが示すクミコ失踪「物語」の帰結としてトオルに強要される。ノボルは、この帰結をトオルに受け入れさせるためにもうつの手段をとる。それはトオルにおける自己像の塗り替え、言わば岡田トオルという「物語」を単純化することである。
複雑な物語を、単純な物語として提示することは、客観性や論理性があると、人々にとって理解がしやすく、受け入れやすくなります(あるいは受け入れざるを得なくなります)。この場面で前述した綿谷昇からオカダトオルへの批判が展開され、オカダトオル自身もある側面ではその通りであると認めています。
しかし、ここで、オカダトオルははいそうですねと引き下がるわけではありません。ここでオカダトオルがやることは、綿谷昇の単純な物語に抗い、物語を複雑化するという方法をとります。
トオルは綿谷昇になんのために3人でここに集まったのか、クミコは家を出てどこに行ったのか、なぜ何も連絡をしてこないのか、といった質問を繰り出し、また、クミコの失踪とは関係のない「下品な猿」の話をして、「物事はそれほど簡単ではない」と答えます。
ここでの対応自体の可否は見方によっては、綿谷昇の方に分があるように見えるかもしれません。なにしろ、オカダトオル自身が認めるように、綿谷昇の指摘は必ずしも間違っていないのです。
しかし、この物事を単純な物語化する、という方法は、非常に示唆に富んだ手法であると感じられます。特に物語の中で象徴的な出来事として、物語のクライマックスで、オカダトオルが壁を抜けて精神世界に入り込んだ時、ホテルのロビーのような場所でテレビが綿谷昇が暴漢に襲われたニュースを見た人々がバットを持った主人公に襲い掛かるシーンがあります。
テレビが伝える綿谷昇を襲った暴漢の姿は、オカダトオルの姿に酷似したものでした。オカダトオルは綿谷昇を襲っていません。しかし、それを証明する術はありません。テレビが言った人物像が目の前に現れれば、疑うことは当然と言えるでしょう(何しろ、野球のバットを持った顔にあざのある男、というかなり特徴的な見た目をしているので、疑いたくなる気持ちはわかります)。
これは、テレビを通して、分かりやすい情報を人々が受け取り、その真偽を確かめぬまま行動してしまう今の社会システムの危うさを表しているようにも思えます。いや、今のではなく戦時のころから、無批判に情報を鵜呑みにすることの危うさというものは変わっていないのかもしれません。だからこそ、簡単な物語に飛びつかず、物事を複雑に考えてみることに意義があるように感じられます。
物語を複雑化する、というと、まるで屁理屈を言っているかのように響きますが、簡単な物語に飲み込まれ、操られてしまわないように、ある面では重要なことなであり、それこそが、オカダトオルの対抗手段として意味のあるものになっています。
まとめ
物語を単純化する、という方法は小説の中だけの話ではありません。むしろ、SNS全盛期の現代こそ、より世の中にはびこっているようにも思えます。人々は物事をわかりやすく簡易に伝える人に魅力を感じるものです。
そのすべてが悪であるとは思いませんが、歴史を振り返ると様々に悪用されてきた手法であるとも言えるでしょう。この小説も読みやすいとはいえ、話の内容は決して簡単なものではありません。しかし、簡単なものではないからと投げ捨ててしまうのではなく、その本質はどこにあるのか、何を表しているのかを深く考えることは重要ではないか、そんなことを感じることのできる小説でした。
想定以上に長い文章になってしまいましたが、ひとまずここで終えたいと思います。ここで書いただけではなく、様々な要素が複雑に絡み合っている小説ですので、とても考察しがいがあって面白い小説でした。
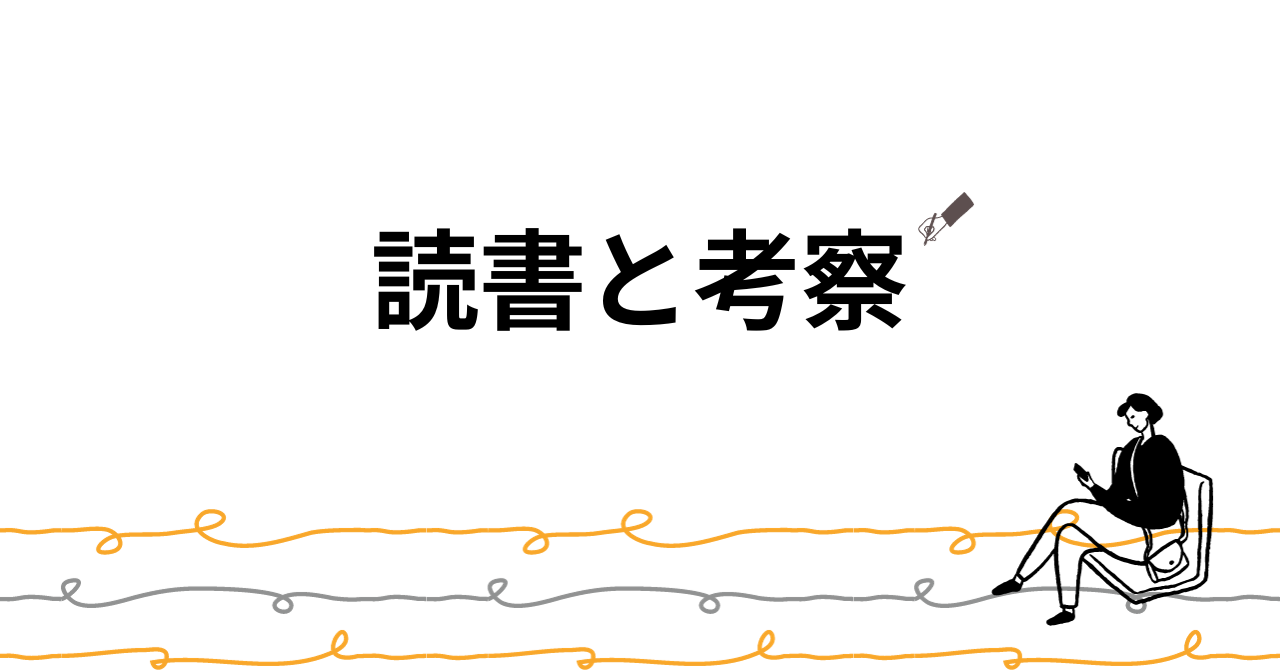


コメント